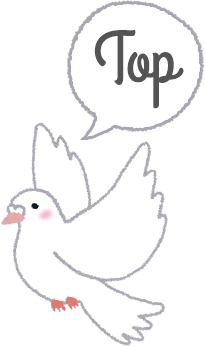ご挨拶/理念
(代表・顧問ご挨拶)
『 Happy スクール 』 代表ご挨拶

放課後等デイサービス『Happy スクール 』 代表の德田幸雄です。生来子供が大好きで、鳥取大学教育学部を卒業後、伊丹市立中学校に20年余、伊丹市立特別支援学校に7年、西宮市立小学校に10年余教職一筋に勤めてきました。この間、障害のある子供達と常に関わりを持ってきました。
昔から私は、障害のある子供達とすぐに仲良くなります。その理由はおそらく、自分が日頃から子供の目線で彼らに寄り添い、一人の人間として共により良く生きようとするからではないかと思っています。
また、同様に彼らの保護者の方にもよく信頼していただきます。困難に面して困っているとき等にその答えを相手にのみ求めることなく、一緒に考えましょう、そして互いの努力で少しずつ解決していきましょうという姿勢を貫いているからかもしれません。
この姿勢は、これこそが福祉社会だと思う私の信念です。
私たちの社会には、「自分が幸せになるためには、一生懸命頑張ってより高い目標を達成することが大切だ。」との成果重視の価値観があふれています。しかし、その目標に達する一部の人以外にも、目標を達成することができない人は数多く存在しています。
私は、人の人生は、高い目標を勝ち取ることだけではなく、自分に合った目標に向かって自分にできる努力を長い年月にわたって継続できるかどうかにかかっていると思っています。目標を持って地道に努力を継続することで様々な能力や人間力が備わり、何より自分にできる努力を地道に継続できる生き方に幸せを感じる事ができるからです。
このことは、その人に障害が有ろうと無かろうと何ら変わることはありません。
放課後等デイサービス『 Happy スクール 』の理念は、 いろいろな活動において『できる』経験を子供たちが少しでも多く経験し、自分に自信を持ち、自分の意志で努力する喜びを味わえるような環境を用意することにあります。これにより子供たちには自己肯定感が育ち、子供たちは自分にできることに積極的に取り組むようになるのです。
放課後等デイサービス『 Happy スクール 』では、 子供たちは将来の進路を見通し、自分が伸びるためにぴったり合った完全個別の課題に毎日取り組んでいます。そして、それができるようになったら次のステップに進みます。
その中で子供たちは自信を取り戻し、課題に取り組むことが楽しくなって主体的に継続して取り組み、長い月日の中で大きな力に積み上がっていきます。
ここでの先生方の支援で重要なことは、「子供たちが『できるようになった』ことをしっかり認めて十分にほめる。」ことと、「子供たちに対して『できなかった』とか『間違っている』などの否定的なメッセージを決して与えないこと。」です。
こうした先生方の支援のおかげで子供たちはとても楽しく活動でき、確かな学力や社会性などの資質が身に付き、数カ月もすれば情緒が安定して落ち着いてきます。
こうして、やがては上記のような大人になって幸せに生きてほしいと願う毎日です。
放課後等デイサービス『 Happy スクール 』は、
下の ⑴ ~ ⑸ の大きなメリットをもってご利用者様のニーズに確実にお応えできる、新しい放課後等デイサービスです。
⑴ お子様が毎日楽しく過ごせる、環境に恵まれた広くてきれいな施設であること。
⑵ お子様の安全・安心を最優先に考え、万全の安全対策を施した施設であること。
⑶ お子様の学力向上と障害改善のために、責任を持って実践する施設であること。
⑷ 保護者の方の悩み、お子様の育ちを支える力をサポートできる施設であること。
⑸ お子様が地域社会の中で活躍できる、共生社会を実現するポリシーを持った施設であること。
是非一度放課後等デイサービス『 Happy スクール 』を見学してみてください。
必ずご満足いただけるものと自信を持っておすすめします。まずは「お電話」か「お問い合わせ」でお知らせください。
フリーダイヤル(通話料無料)0800-000-0801(オー ハッピー)
皆様とご一緒に豊かな福祉社会を実現できることを心待ちにしています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
放課後等デイサービス
『Happy スクール』
代 表 德 田 幸 雄
『 Happy スクール 』 顧問ご挨拶
放課後等デイサービス『 Happy スクール 』顧問という大役を仰せつかりました秋元雅仁です。私は元々宝塚市の小学校で教鞭をとっていましたが、転勤で赴任した伊丹市立伊丹養護学校での障害児教育にすっかりはまり、それから18年間もお世話になりました。
毎日毎日が面白くてたまらなかったその頃にお出会いし、後輩教員として日々を共にさせていただいたのが本スクール代表の徳田先生です。気が付けば德田先生とのお付き合いは25年にもなります。
その後それぞれ異なった道を歩み、私は伊丹市の小学校教員、兵庫県立芦屋特別支援学校や兵庫県立こやのさと特別支援学校の教員を経て、現在、三重県伊勢市にあります皇學館大学教育学部教育学科特別支援教育コースで准教授として、未来を支える教師づくりに取り組んでいるところです。
一方、伊丹市におきましても、身体障害者や知的障害者あるいは精神障害者たちの地域での暮らしを支えたいと願い、小規模ながら就労継続支援B型事業所を経営しており、2019年には開設から20年目を迎えます。
1981年、この年は、障害者の『完全参加と平等』をスローガンとした「国際障害者年」が国連から位置付けられた年です。大学を出たばかりの私は、それ以前の1979年に養護学校が義務化されたことさえ十分には知っていませんでした。
それ以降今日まで、障害者施策を取り巻く国際情勢は目まぐるしく変遷しました。 25年後の2006年、第61回国連総会において「障害者の権利に関する条約」が採択され、わが国も国内法の整備を終え2014年1月に批准しています。
この条約が求めているものは、共生社会の実現に向けた公平な社会形成のための、合理的配慮および必要な支援の提供、ユニバーサルデザインの採用だと言われています。
教育に関してもインクルーシブな教育システムを構築するための合理的配慮や必要な支援の提供、教育におけるユニバーサルデザインの採用などが求められています。
国内的には「障害者の差別を解消するための法律」が施行され、障害を理由とする差別の禁止と必要に応じた合理的配慮の提供が義務付けられました。
障害者の就労支援が活発化する中、障害者の社会自立や社会参画が声高に叫ばれるようになってきています。
しかし、自分一人でできることの数の多さが「自立」と呼ばれるのであれば、一人でできることが少ない寝たきりの重度障害者や難病患者あるいは後期高齢者らにとっては、何とも生きにくい社会でしかありません。
新たな共生社会を構築するためには、
「一人ではできないけれど、助けてもらえればできる」
「今は助けてもらわないとできないけれど、繰り返しているうちに自分でできるようになるかもしれない」
と誰もが思える、そんな助けや支えが必要です。
このような助けや支えを合理的配慮と呼んでいます。
私のモットーは、こんな助けや支えがあれば自分にもできるという、
『あればできるを支える』です。
そんな思いで毎日学生指導に取り組んでいます。
顧問として何ができるのか見当もつきませんが、本スクール代表の德田先生と共に手を携え、お子様と保護者の方のサポートに尽力させていただくと共に、共生社会の実現に向けて一歩ずつ努力する所存です。
なにとぞ宜しくお願い致します。
皇學館大学教育学部
准教授 秋元雅仁